日本科学技術連盟が発行する日本で唯一のQCサークル専門誌「みんなと改善QCサークル」の2025年11月号 トヨタ自動車㈱東富士研究所「e→モビ サークル」体験事例 の編集のお手伝いをしました。
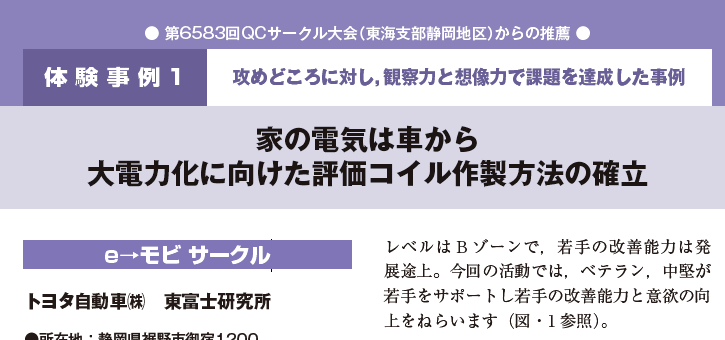
この事例は、
「攻めどころに対し、鋭い観察眼と創造力で課題を達成した事例です。従来の仕様を超えた新しい価値を創造するために、絞り込みや成功シナリオの錬成が参考になります。若手をベテラン・中堅でサポートして進めることで、高い改善能力をもつ人材を育成できました。」
という内容です。
トヨタさんは全社をあげてQCサークル活動を行っており、特に研究開発部門は「従来のやり方にとらわれない新規創造」が必要なため、「課題達成型QCストーリー」を使う事例が多い印象です。さすがトヨタさんですね。
「課題達成型QCストーリー」では、まず、「ありたい姿」を定量的に定め、現状とのギャップを分析し、もっとも改善すべきところの「攻め所」を明確化し、対策を立案していきます。
「ありたい姿」の理想を掲げるだけでは、人によって解釈や目標が変わり、最後になって「つじつまあせわ」になりがちなので、ここを具体的に定量化(見える化)するところが最初のポイントです。
方策立案でも、たくさんの方からアイディアを集め、それを皆で検討・議論することで新たなアイディアが出ることがよくあります。最初から「やることありき」で進めると議論にならないし、それはQCサークル活動の趣旨からもはずれるので、「やること」は一つのアイディアとして議論するといいですね。
また、この事例では、PDPC法やアローダイアグラムなど新QC七つ道具も使いこなしています。
両手法は聞きなれない方や、知っていても実際に使ったことがない方が多いと思いますが、実はそれはプロジェクトを進めるときに、プロジェクトリーダーが頭の中で考えていることそのものなんです。
それを皆が共通に理解できるように図示(可視化)する一つのフォーマットですね。
書き方のルール(ガイドライン)はあるのですが、それにとらわれず、サークルメンバーが誤解しないならアレンジOKというのが僕のスタンスです。
編集は、原本を要約・図表の選択・学びどころ(解説)の挿入など行い、規定ページに収まるように配置します。まとめのコメントは以下のようにしました。
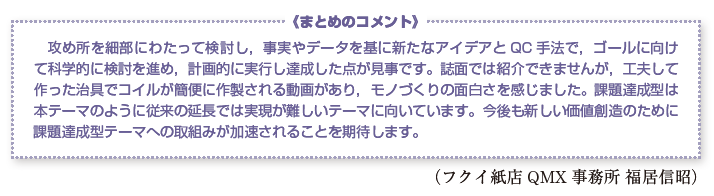
一つ一つの文が長いのは反省です。
既定の文字数内でめいっぱい詰め込もうとしてしまいました、、、
要約力・文書力がまだまだですね、、、
なお、11月号の特集は「役立つQC七つ道具にする教え方」です。
QC七つ道具の使い方のポイントが説明されており、大変参考になります。
ぜひご一読ください。
コメントお待ちしております。
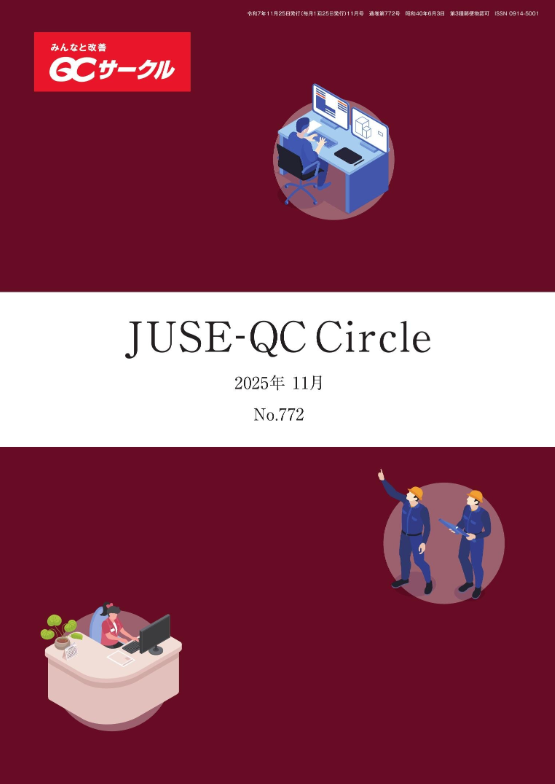


コメント